こんにちは、とめです。
データ分析を独学で学び、未経験からデータアナリストへ転職し、今では本業をやりながら、副業でも活動しています!
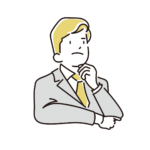
データ分析を始めたいけど、“統計”って難しそうで、どこから学べばいいのか分からないんだよね…。

初めてのデータ分析をする場合、統計は3つの統計を学んでおくのがオススメだよ。
データ分析を学ぶ上で欠かせないのが統計の基礎知識です。
しかし、多くの初心者が「専門用語が多くて難しそう」「数式ばかりで挫折しそう」と感じてしまいますよね。
そこで今回は、データ分析に役立つ3つの統計を、初心者でもイメージで理解できるようにわかりやすく解説します。
私自身も、もともとは文系出身・未経験から独学で統計を学び、現在はデータアナリストとして企業データの分析を行っています。
そんな実体験をもとに、「どの統計をどんな場面で使えばよいか」を、ビジネスや日常での具体例とともに紹介します。
- 統計の3つの種類と役割の違いが理解できる
- 自分の仕事にどの統計が必要か判断できる
- データ分析を始めるための最初の一歩が踏み出せる

「統計って難しそう…」という不安を、自信に変えていこう!
統計とデータ分析の関係とは?

統計はデータ分析の土台となる最重要スキルです。
膨大なデータをそのまま眺めても意味を見いだせず、数値を要約して特徴をつかみ、将来を予測する仕組みが必要だからです。
例えば、売上データを分析するとき、
- 「平均はいくらか?」(全体像を把握)
- 「来月も同じ傾向が続くのか?」(将来の予測)
といった疑問に答えるのが統計の役割です。
ただ、一口に統計と言っても、統計には3つの統計があり、その特徴や目的、役割などを理解した上でデータ分析を行う必要があります。
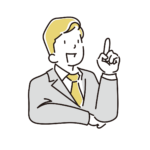
つまり“統計を学ぶ=データ分析の地図を手に入れる”ってことですね!

その通り!3つに分けて覚えれば迷わず進めます!
データ分析に使える3つの統計
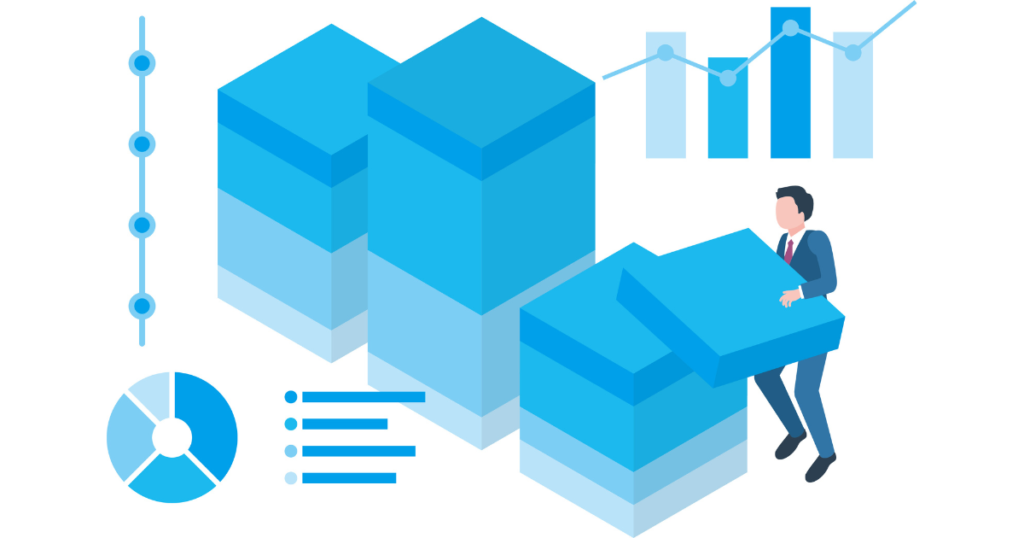
データ分析をするうえで、覚えておきたい統計は、以下の3つです。
- 記述統計
- 推測統計
- ベイズ統計
記述統計
記述統計とは、データをわかりやすく整理・要約するための統計手法です。
平均・中央値・分散などの代表値でまとめることを指します。
たとえば、社員一人ひとりの残業時間をすべて並べても、誰が多いか少ないかは分かっても「会社全体の傾向」は見えてきません。
しかし、平均値を算出すれば「平均残業時間が20時間」というように、組織全体の働き方の特徴を明確に把握できます。
これが記述統計です。
▼記述統計でよく使われる主な指標
| 種類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 平均値 | 全体の中心的傾向を示す | 社員の平均残業時間 |
| 中央値 | データの真ん中に位置する値 | 年収の中央値 |
| 分散・標準偏差 | データのばらつきを示す | 売上の月ごとの変動幅 |
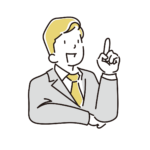
平均や中央値って“データの性格”を知るためのヒントになるんだね!

そう!数値を“まとめて伝える力”が記述統計の魅力なんだ!
記述統計はすべてのデータ分析の出発点。
どんな高度な分析を行う場合でも、まずは記述統計でデータの特徴を“見える化”することが成功の第一歩です。
推測統計
推測統計とは、一部のデータから全体の傾向や未来を予測するための統計です。
ビジネスや社会では、全員分のデータを集めることは難しく、時間もコストも膨大になります。
そのようなときに使うのが推測統計です。
推測統計では、全員分のデータの代わりに「サンプル(標本)」を抽出し、限られたデータから母集団(全体)の特徴を推定します。
- 選挙の世論調査:全国民に聞かなくても、一部の有権者の意見から全体の傾向を推測できる。
- A/Bテスト:広告やWebページの新デザインが有効かどうかを、一定のサンプルで比較・検証できる。
- 品質検査:全製品を調べず、ランダムに抜き取って不良率を推定する。
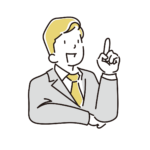
たった一部のデータで全体を予測できるなんて、まるで“未来を覗くレンズ”みたい!

そうそう!でも正確に推測するには“適切なサンプル数”と“偏りのないデータ”が大事なんだ。
推測統計はデータ分析に“未来を見通す力”と“意思決定の裏付け”を与えるものです。
売上予測・マーケティング戦略・顧客行動分析など、あらゆる分野で欠かせないスキルといえるでしょう。
ベイズ統計
ベイズ統計とは、新しい情報が得られるたびに確率を更新し、より正確な判断を行う統計手法です。
状況が変わるたびに新しいデータを取り入れ、推定を見直す必要がある場合にこの統計を利用します。
たとえば、以下のような場合でベイズ統計はおすすめです。
- 医療診断:初診で病気の可能性を50%と推定。追加検査の結果が陽性なら、その確率を70%や80%に“更新”
- スパムメール判定:新しいメールデータを読み込むたびに、学習内容をアップデートし、判定精度を高める
- マーケティング分析:広告クリック率などの新しいデータを反映し、次回の施策効果をより正確に見積る
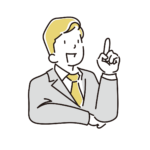
ベイズ統計って、一度出した答えを状況に応じて修正できるのがポイントなんだね!

そう!確率を更新する考え方が、ベイズ統計の最大の魅力なんだ!
ベイズ統計では、「事前確率」→「新しい情報」→「事後確率」という流れで考えます。
▼ベイズ統計の流れ
| 用語 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 事前確率 | まだ情報が少ない段階での予想 | 病気の発症確率は10%程度 |
| 新しい情報 | 検査・データなどの追加情報 | 検査結果が陽性 |
| 事後確率 | 情報を反映した新しい確率 | 発症確率が60%に上昇 |
ベイズ統計は「柔軟に学習し続ける」分析を可能にします。
AI・機械学習・マーケティング最適化など、変化の激しい現場でこそ真価を発揮する統計手法です。
3つの統計の違いと使い分けまとめ

記述統計・推測統計・ベイズ統計は、それぞれ目的と使い方がまったく異なります。
- 記述統計:データを「まとめて見える化」する
- 推測統計:一部のデータから「全体を予測」する
- ベイズ統計:新しい情報で「確率を更新」する
この3つを理解すると、データ分析で「どの手法を使えばいいか」が明確になります。
▼シーン別の使い分け例
| 状況 | 適した統計 | 理由 |
|---|---|---|
| アンケート結果を整理したい | 記述統計 | 平均値や割合で全体像を把握できる |
| 新しい広告の効果を確かめたい | 推測統計 | サンプル結果から全体の反応を推定できる |
| ユーザー行動が日々変化している | ベイズ統計 | 新しいデータに応じて判断を更新できる |
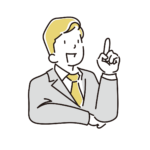
なるほど!
“現状を整理”するのが記述、“未来を読む”のが推測、“変化に対応する”のがベイズってこだね!

その通り!
3つを理解して使い分ければ、どんなデータも“意思決定の材料”に変えられるよ!
学ぶ順番は「記述 → 推測 → ベイズ」がオススメです。
まずはデータを整理(記述)、次に全体を予測(推測)、最後に柔軟に更新(ベイズ)と進めることで、理解も実践も格段にスムーズになります。
まとめ:統計の種類を理解してデータ分析を始めよう!

本記事では、データ分析に欠かせない3つの統計(記述統計・推測統計・ベイズ統計)について解説しました。
それぞれの役割をもう一度整理すると、以下になります。
- 記述統計:データをわかりやすく要約して全体像をつかむ
- 推測統計:サンプルから全体を予測し、意思決定に活かす
- ベイズ統計:新しい情報を反映しながら、確率を柔軟に更新する
この3つを理解することで、データを見る視点が広がり、数字から“意味”を読み取る力が身につきます。

各統計の役割を理解して、使い分けるのが大事なんだね!

その通り!
先ずは、“記述 → 推測 → ベイズ”の順に学んで、分析の流れを掴もう!
順を追って学べば、仕事や日常の中で「この場合はどの統計を使えばいいか」を判断できるようになります。
データ分析は、“数字を扱う力”が“未来を描く力”に変わる世界です。
今日から、学びを一歩ずつ始めてみましょう。

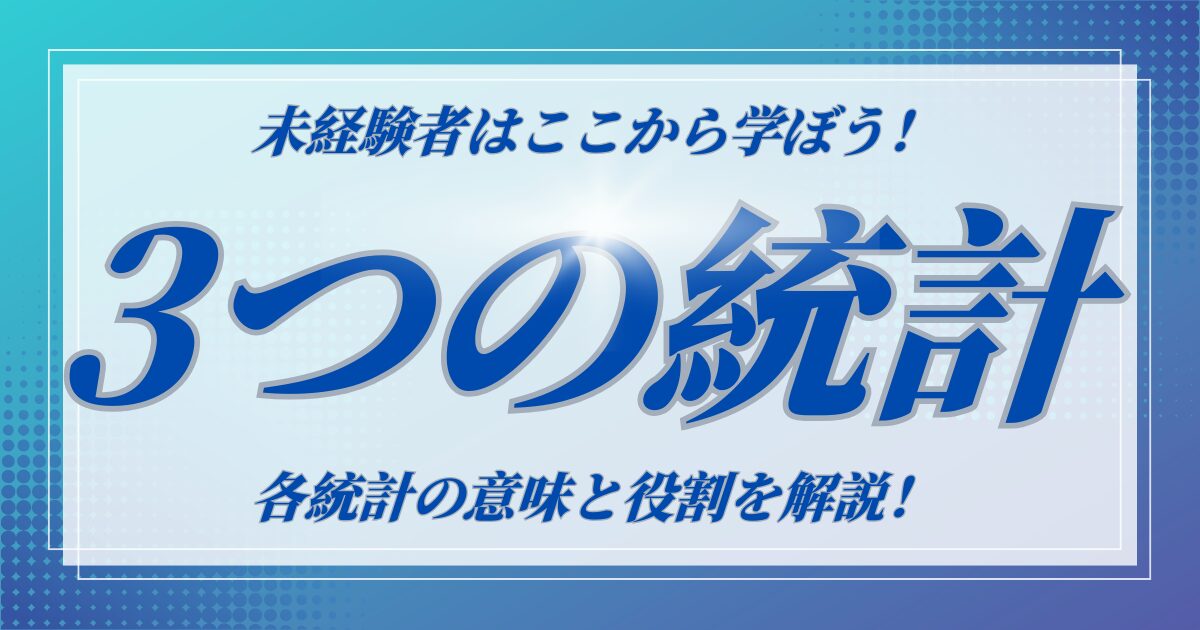


コメント