こんにちは、とめです!
データ分析を独学で学び、未経験からデータアナリストへ転職し、今では本業をやりながら、副業でも活動しています!
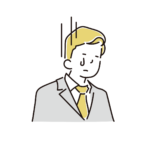
データ分析しているんだけど、何のために分析しているか途中でわからなくなるんだよね…。

それは、データ分析の目標設定ができていなからだよ!
データ分析は“目標設定”を誤ると、どれだけ時間をかけても“分析のための分析”で終わってしまいます。
正しく目標を設定できればすることで、以下のような効果があります。
- 必要なデータが明確になり、無駄な作業が減る
- 成果を定量的に示せるため、周囲からの信頼が高まる
- ビジネスの成長に直結する意思決定が可能になる
私も未経験からデータアナリストとなり、数多くの分析プロジェクトに関わってきました。
その経験から断言できるのは、成果を出す分析は必ず「明確な目標設定」から始まっているということです。
この記事では、データ分析における目標設定の方法を、SMARTの法則やKGI・KPIの整理、仮説ドリブンの考え方など具体例を交えて分かりやすく解説します。

目標設定の作り方をマスターしよう!
データ分析における目標設定がなぜ重要か

データ分析の目標設定が重要である理由は「成果を出すための最初の一歩」であり、これが曖昧だと、分析は迷走し価値を生み出せないからです。
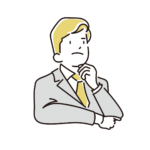
目標設定しない分析をしたらどうなるの?
目標が不明確なまま分析を始めると、以下のような問題が起こります。
- どのデータを集めれば良いのか分からない
- 分析の途中で方向性がぶれてしまう
- 成果を数値で示せず「なんとなく改善した」で終わる
これでは、せっかくの分析も意思決定に活かせません。
つまり、目標設定がないデータ分析は、地図を持たずに旅に出るようなものです。
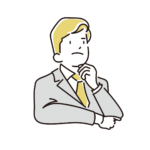
でもさ、データを見れば自然に答えが出てくるんじゃないの?

それが落とし穴!
目的がないままデータをいじると、“で、結局何が分かったの?”で終わっちゃうんだ。

なるほど…。地図なしで旅に出るみたいなものってそういうことか。

その通り!ゴールが見えなければ、どこにたどり着いても評価できないんだよ。
一方、目標をしっかり設定してから分析を始めると、以下の効果が得られます。
- 必要なデータが明確になる → 集計や抽出が効率化
- 分析の方向性が安定する → プロジェクトが進めやすくなる
- 成果を定量的に示せる → 経営層や現場からの信頼が高まる
目標設定は分析の出発点であり、同時に成果を測る基準でもあるのです。
データ分析での目標設定の作り方

データ分析を行う上で、正しい目標設定のやり方は以下、5つのポイントがあります。
- SMARTの法則で目標を明確化する
- KGIとKPIを整理する
- 仮説ドリブンで目標を立てる
- ステークホルダーと合意形成する
- 小さく試して改善する
SMARTの法則で目標を明確化する
目標設定一番、重要なのは目標を明確にすることです。
SMARTの法則を使えば、曖昧な目標を「実行可能で測定可能なゴール」に変えられます。
なぜなら、SMARTの法則は目標設定のフレームワークで、5つの視点から整理することで曖昧さを防げる事ができるからです。
▼SMARTのの法則
| 要素 | 意味 | データ分析でのポイント |
|---|---|---|
| S:Specific(具体的) | 誰に・何を・なぜを明確にする | 「売上を上げる」ではなく「新規顧客売上を10%増やす」 |
| M:Measurable(測定可能) | 数値で進捗を測れるようにする | 「満足度を上げる」ではなく「NPSを+5改善」 |
| A:Achievable(達成可能) | 実現可能な範囲に設定する | 市場やリソースに基づき現実的に設定 |
| R:Relevant(関連性) | ビジネスや課題に直結させる | 部署や全社の目標に紐づける |
| T:Time-bound(期限付き) | 期限を決めて進捗を管理する | 「半年以内に」「3か月で」など期限を設定 |

SMARTの法則は、データ分析の目標設定以外にも使えるから、ぜひ覚えてね!
曖昧な目標をSMARTに沿って整理すると、下記のように行動可能な目標に変わります。
- サイト訪問者数を増やす ▶ 3か月以内に広告キャンペーンで月間訪問者数を20%増加させる
- 売上を上げる ▶ 年末までに新規顧客経由の売上を前年比15%増加させる
- 顧客満足度を改善する ▶ 半年以内に顧客アンケートの平均スコアを4.2から4.5に改善する
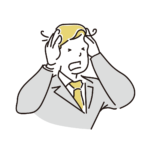
SMARTってなんか難しそう…。5つも覚えられるかなあ。

大事なのは“数字と期限を入れる”ってことだけ覚えればOKだよ!
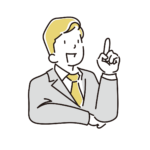
なるほど!『いつまでに、どれくらい』を入れるって覚えればシンプルだね。

そうそう。細かいフレームワークは後から慣れていけばいいんだ。
SMARTを取り入れることで、誰でも“曖昧な願望”を“実行可能な目標”に変えられます。
これがデータ分析の成功に直結するので、覚えておきましょう。
KGIとKPIを整理する
データ分析では「KGI(最終ゴール)」と「KPI(途中の指標)」を分けて考えることで、全体像と具体的な改善ポイントの両方を押さえられます。
なぜなら、ゴールと道しるべを混同すると、分析の方向性がぶれてしまうため、それぞれを明確に切り分ける必要があるからです。
- KGI(Key Goal Indicator):最終的に達成したいゴール
例:年間売上1億円を達成する - KPI(Key Performance Indicator):KGIを達成するために追うべき途中の指標
例:新規顧客獲得数、CVR(コンバージョン率)、リピート率
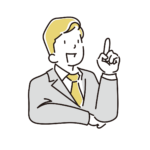
つまり、KGIは“目的地”、KPIは“目的地までの道しるべ”と考えれば分かりやすいね!
具体的には、下記のようにKGIとKPIをセットで設計していくと、分析の意味が明確になります。
▼例)KGIとKPIの関係性
| KGI(最終ゴール) | KPI(追うべき指標) |
|---|---|
| 年間売上1億円達成 | 新規顧客獲得数、顧客単価、リピート率 |
| サイトCV数を10,000件にする | PV数、CTR、フォーム完了率 |
| 離脱率を10%改善する | ページ滞在時間、直帰率、NPSスコア |
このように、KGIがあるからこそKPIに意味が生まれるのです。
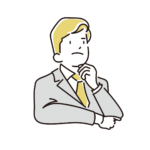
KPIを追ってるけど、正直“意味あるのかな?”って思うときがあるんだよね。

それはKPIがKGIにつながっているかを確認できてないからだよ。
KGIが“ゴール”で、KPIは“ゴールまでの道のり”なんだ。
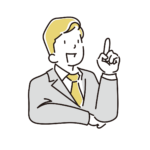
なるほど!じゃあKGIを最初に決めて、そこに向かってKPIを並べるイメージだね。

その通り!それができると分析の意味が一気に明確になるよ。
つまり、データ分析の目標設定では、必ずKGIを先に決め、その達成に必要なKPIを設計することで、効果的かつ一貫した分析が可能になるということです。
仮説ドリブンで目標を立てる
データ分析の目標は「仮説ベース」で設定することで、迷走を防ぎ、効率的に進められます。
仮説を立てずにデータを扱うと、方向性を失いやすく、時間だけが無駄になりやすいです。
初心者に多いのが「とりあえずデータを集めてから考える」というやり方です。
しかし、この方法には以下のリスクがあります。
- データを眺めるだけで時間が過ぎてしまう
- 重要でない指標を追いかけてしまう
- 分析結果が「だから何?」で終わってしまう

つまり、仮説なしで分析を始めると、目的地のない探索に迷い込む危険がある。
分析が目的にならないように、仮説を立てた分析をしよう!
具体的には以下のように、データ分析は「仮説 → 検証 → 改善」のサイクルで進めると効果的です。
- 仮説を立てる:「この施策が効いているはず」「この要因が課題では?」
- 検証する:KPIを設定し、データで確かめる
- 改善する:結果をもとに施策を修正し、再度検証する
このサイクルを繰り返すことで、分析はビジネスに直結する具体的なアクションにつながります。
例:「新規顧客の定着率が低いのは、初回購入後のフォロー不足ではないか?」
- 仮説 → 初回購入者へのメール施策が足りない
- 検証指標 → 初回購入者の2回目購入率
- 改善 → フォローアップメールを追加し、効果を測定
このように、仮説ベースでKPIを設定すると、分析の無駄が減り、成果に直結するのです。
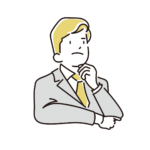
なるほどね。
僕、いつも“とりあえず全部のデータを見てみよう”って始めてた。

それだと迷子になるよ。
まず“どんな仮説を検証したいか”を決めないと、データに振り回されるだけだよ。

うん!
仮説を立ててからデータを見るように意識してみる!
データ分析では“まず仮説ありき”。
仮説を軸にKPIを設計することで、効率的かつ成果につながる目標設定ができます。
ステークホルダーと合意形成する
データ分析の目標は一人で決めるのではなく、ステークホルダーと合意形成することで価値が最大化します。
関係者の視点がずれたまま分析を進めると、成果が正しく評価されず無駄になるからです。
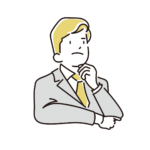
自分たちで目標を決めて、仮説を立てて、分析した結果を報告しちゃダメなの?
目標を分析担当者たちだけで決めてしまうと、以下のような問題が発生します。
- 経営層と現場で「成功の定義」が食い違う
- 分析結果を現場が活用せず、自己満足で終わる
- 成果が出ても「期待していたものと違う」と評価されない
このように、合意形成が欠けると、どれだけ分析が正しくても価値は半減するのです。
そのため、効果的に合意形成をしていくためには、次のプロセスを取り入れて行きましょう。
- 成功の定義を明文化する:「売上◯%アップを成功とする」など、誰もが理解できる形にする
- 役割を整理する:経営層(方向性)、現場(実行)、アナリスト(分析)
- 定期的にレビューする:進捗や成果を共有し、必要に応じて目標を修正する

これを事例イメージに落とし込むと、以下のようになるよ。
- 経営層:「新規売上を前年比20%伸ばしたい」
- 現場担当者:「広告施策の改善を行う」
- アナリスト:「CTR・CVRをKPIに設定して効果を測定し、進捗・共有する」
このように役割を分けて合意を取ることで、目標が全員にとって納得感のあるものになるのです。
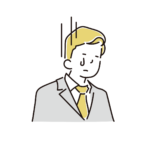
言われてみれば、前に分析結果を出したとき、“現場が欲しかった答えじゃない”って言われたことある…。

“成功の定義”が共有されてないパターンだね。
最初に関係者と合意しておけば防げたはずだよ。

うん!
次からは、最初に“何を成功とするか”を一緒に決めていくよ!
データ分析の目標設定は、関係者との合意をベースに進めて、実用性を持つようにしましょう。
小さく試して改善する
データ分析の目標設定は、一度で完璧に仕上げる必要はなく、小さく試して改善を繰り返すことが現実的で効果的です。
なぜなら、実務の現場では状況が変化しやすく、最初から完璧な目標を立てるのは困難だから。
- データを実際に扱ってみないと分からないことが多い
- ビジネス環境が常に変化する
- 立てた仮説が外れることもある

だから、小さく試して修正する前提で目標を立てることが重要なんだよ!
また、小規模な検証から始めることで、以下のメリットが得られます。
- 低コストで検証できる
- 早い段階でフィードバックが得られる
- 失敗しても影響が小さい
- PDCAを回しやすい
たとえば「3か月でCVRを20%改善」という大きな目標も、まずは「1か月以内に広告A/Bテストを実施し、改善幅を確認する」といった小規模検証から始めることで、目標達成の確実性が増すのです。

また、改善する時の流れは以下を意識しましょう。
- 小規模で実行する
- 結果をステークホルダーと共有する
- フィードバックを反映して目標を修正する
このループを繰り返すことで、目標は徐々に現実的かつ成果につながる形に進化していきます。
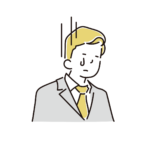
僕、いつも最初から完璧な目標を立ててしまうクセがあったよ…

それだと現実味がない。
まずは小さく試して修正する方が、現実的で失敗も減るんだ。
データ分析の目標は“最初から完璧にする”のではなく、“小さく試して改善する”ことで初めて成果につながります。
まとめ:データ分析の目標設定は「明確さ」と「実行性」がカギ

今回は「データ分析における目標設定」について解説しました。
- SMARTの法則で曖昧な目標を具体化できる
- KGIとKPIを整理することで、全体像と改善ポイントを押さえられる
- 仮説ドリブンで目標を立てると、無駄な分析を防げる
- ステークホルダーとの合意形成が分析を成功に導く
- 小さく試して改善を繰り返すことで、現実的に目標を育てられる
データ分析における目標設定は「具体的で測定可能な目標を立て、関係者と合意し、改善を繰り返すプロセス」です。
このプロセスを取り入れることで、分析の成果は「なんとなくの改善」ではなく、ビジネス成長に直結する実用的な成果に変わります。

大きいことをする前に、小さいことから始める意識をしてみるよ!

いいね!
まずは、プロジェクトの目標をSMARTに書き直してみることから始めてみよう!
以上、とめでした!
▼勉強時間を捻出する方法
▼キャリア設計のやり方
▼未経験からデータアナリストになる心構え
▼未経験からデータアナリストになるための10ヶ条
▼SQLの始め方

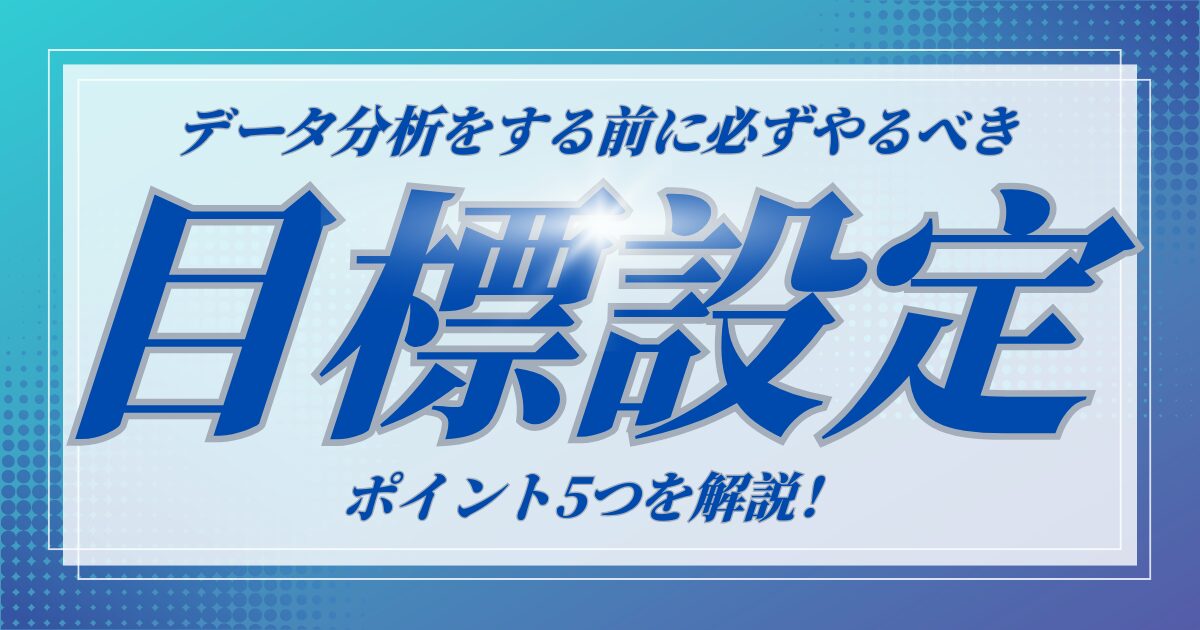
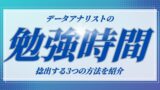
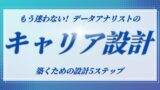
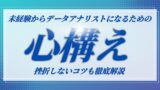




コメント